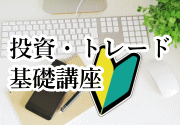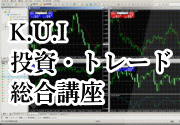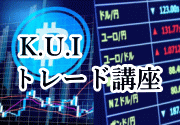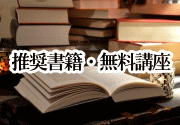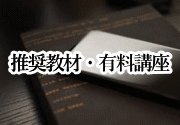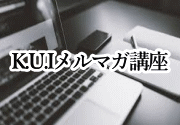なぜグランビルの法則では勝てないのか。設定値の落とし穴。
グランビルの法則は移動平均線とレートの推移から捉える事ができるチャートパターンの1つです。
移動平均線によるチャートパターンとしては「ゴールデンクロス」「デッドクロス」などが有名ですが、グランビルの法則との大きな違いは、
・「ゴールデンクロス」「デッドクロス」は短期、長期の移動平均線で捉える
・「グランビルの法則」は移動平均線と現在レートの推移で捉える
といった違いがあり、この「違い」がそれぞれのチャートパターンの有効性や特性を大きく左右しています。
この記事では、後者の「移動平均線と現在レートの推移」による『グランビルの法則』の方をフォーカスする形で解説していきたいと思います。
***
ゴールデンクロス、デッドクロスのシグナルについては以下の記事で詳細を解説していますので、こちらの記事も併せて参考にしてください。
「グランビルの法則」の有効性について。
グランビルの法則は4つの「買い目線」のチャートパターンと、その上下を真逆に見た場合の「売り目線」のチャートパターンがあり、以下が、その「買い目線」の4つのチャートパターンに該当します。法則-1:上向きの移動平均線をレートが下から突き抜ける
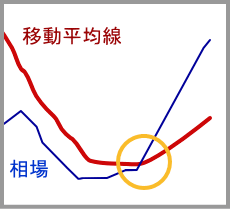
法則-2:上向きの移動平均線にレートが上から接近、接触して方向転換する
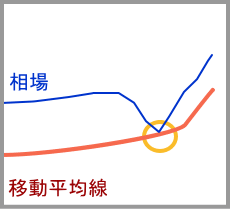
法則-3:上向きの移動平均線をレートが上から下に抜け、再び上方向に転換する
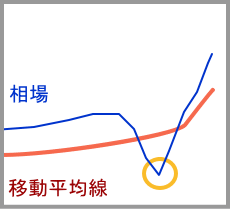
法則-4:移動平均線から離れたレートが移動平均線側に方向転換する
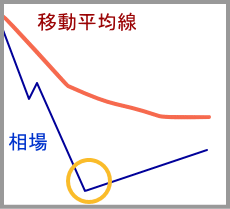
これらに該当するチャートパターンとなった場合において、相場が上昇するという「傾向」をグランビルの法則というわけですが、一般的には、各チャートパターンの「黄色の〇印」のポイントが「買い」のポイントと言われています。
よって、この上下の目線を真逆にしたものがグランビルの法則における「売り目線」のチャートパターンという事です。
その上で、この「グランビルの法則」が、なぜ、有効性が伴うチャートパターンと言われているのか、という点については『移動平均線の仕組み(ロジック)』が、そこに関係しています。
そもそも移動平均線は「平均レートの推移」をチャート上に示しているインジケーターに他ならないため、その平均レートの計算対象となった期間のみに着目すれば、現在レートが移動平均線の「上」にある状況は、
・その期間内に建てられた買いポジション全体で含み益が出ている
・その期間内に建てられた売りポジション全体で含み損が出ている
という視点で相場を捉える事ができます。
逆に現在レートが移動平均線の「下」にある状況は、
・その期間内にに建てられた買いポジション全体で含み損が出ている
・その期間内に建てられた売りポジション全体で含み益が出ている
という視点で相場を捉える事ができるわけです。
ただ、ここで注意するべき点として「移動平均線」を形成している平均レートには、その期間ごとの出来高(取引量)が、各平均レートの算出値に反映されているわけではありません。
要するに「移動平均線」と「現在レート」の位置関係による買いポジション、売りポジション全体の含み益、含み損状況の把握は、あくまでも平均レートのみを捉えた「目安」でしかないという事です。
とは言え「移動平均線」と「現在レートの位置」から、その時点の買いポジション、売りポジション全体の「傾向」は、ある程度の目安として捉える事ができるため、グランビルの法則における、
法則-1:上向きの移動平均線をレートが下から突き抜ける
法則-2:上向きの移動平均線にレートが上から接近、接触して方向転換する
法則-3:上向きの移動平均線をレートが上から下に抜け、再び上方向に転換する
この3つのチャートパターンに該当する状況はいずれも、現在レートと移動平均線が「接近」または「接触」する状況を前提としています。
つまり、
・対象期間内に建てられた買いポジション全体で常に含み益が出ている状況
・対象期間内に建てられた買いポジション全体の含み損が含み益に転換した状況
このような視点で相場を捉える事ができる状況を意味しているため、こうした状況下におけるトレーダーの心理や実際の動向としては、
・含み益が出始めた人は買いポジションを解消する事なく保持する。
→ 売り注文が減る
・含み損が出始めた人、膨らみ始めた人は売りポジションの解消に動く
→ 売り注文を解消するための買い注文が増える
このような判断や動向に至っていく可能性が高いという見方が出来ます。
故に、グランビルの法則に基づく「買い目線」のチャートパターンが生じた相場では、売り注文が減り、買い注文が増えていく事によって、相場が上昇傾向になる可能性が高いという法則が提唱されているわけです。
移動平均線とレートの位置関係によるバイアス = グランビルの法則
ただ、グランビルの法則として挙げた、以下の4つ目のチャートパターンは、先立つ3つのチャートパターンに対して、やや法則上の理論的な背景が異なります。法則-4:移動平均線から離れたレートが移動平均線側に方向転換する
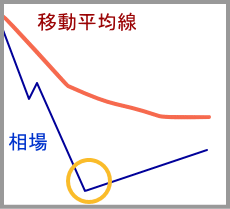
この4つ目のチャートパターンは、
「平均レートよりも現在レートが下がり過ぎている状況」
「売りポジション全体において大きな含み益が出ている状況」
という点で「移動平均線とレートの乖離(それぞれの距離が離れた状況)」と「その反動(戻り相場)」を狙ったサインとなっています。
このような状況下におけるトレーダー心理としては、
・安くなったレートを狙って新規の買いポジションを建てる
→ 買い注文が増える
・それを見越して十分な含み益が出ている売りポジションが解消される
→ 売り注文を解消するための買い注文が増える
このような判断や動向に至る可能性が高いという見方が出来る事になります。
故に、このチャートパターンにおいても、売り注文が減り、買い注文が増えていく事によって、相場が上昇傾向になる可能性が高いという法則が提唱されているわけです。
ただ、このようなグランビルの法則に沿ったチャートパターンは、あくまでも、特定の時間足のチャート上に表示された、特定のパラメーター設定による移動平均線による経過状況でしかありません。
そもそも、このグランビルの法則を担っている「移動平均線」というテクニカル指標は、トレーダーが表示している時間足や移動平均線のパラーメーターで形状が異なってしまうインジケーターです。
よって、必然的にグランビルの法則に沿ったチャートパターンの有無やタイミングは、各トレーダーの時間足チャート、移動平均線のパラメーター(設定)次第で大きく変わってしまいます。
つまり、この「グランビルの法則」のような移動平均線によるチャートパターンに『だまし』が多いとされる要因として、
・主軸としている時間足チャート
・そのチャート上に表示している移動平均線のパラメーター
これら「差異」がある以上、あらゆる時間足のあらゆる移動平均線による値動きが、全て、その「法則」の通りになるはずがありません。
故に、その「違い」によって、そのチャートパターンが有効となるケースもあれば、騙しで終わるケースもあるわけです。
とは言え、ローソク足チャートの「時間足」や移動平均線の「パラメーター」は、一定数の多くのトレーダーが共通して見ているとされる時間足や移動平均線が無いわけではありません。
そこを踏まえた上で「有効」となる移動平均線の使い方が、
「長期、中期、短期とそれぞれの移動平均線を複合的に分析する」
という方法であり、この方法はグランビルの法則を捉える上でも有効となります。
そのような移動平均線の複合分析や、そのような視点を前提とした形のグランビルの法則の実用については、以下の記事で詳しい方法などを解説していますので、こちらも併せて参考にして頂ければと思います。
***
ちなみに私が推奨している情報商材の1つ、
『FXism及川デイトレ大百科』
において提唱されているトレード手法は、この「移動平均線の複合分析を突き詰めたトレードノウハウ」となっています。
>FXism及川デイトレ大百科(及川圭哉)レビュー記事はこちらから
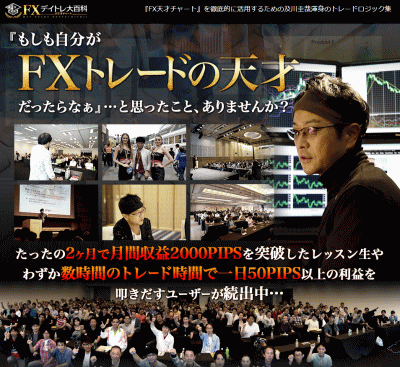
もし、興味があれば、こちらのレビュー記事の方にも目を通してみてください。
あなたにとって「必要な情報」を存分に学んで帰ってください。
以下に、このブログの「目次」にあたるコンテンツ一覧のページをご用意していますので、こちらから「あなたにとって必要な情報(価値がありそうな情報)」を是非、存分に収集して頂ければと思います。>投資家K.U.I(近藤勇一)Official BLOGコンテンツ一覧ページ
タグ:移動平均線