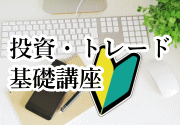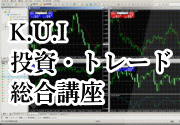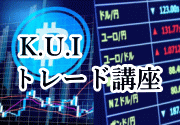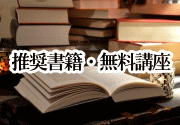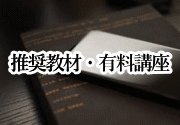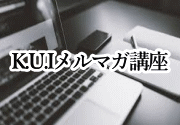ダイバージェンス オシレーター系インジケーターの注意点。
テクニカル分析に用いるテクニカル指標(インジケーター)は、
・トレンド系インジケーター
・オシレーター系インジケーター
これらに大別されると言われています。
トレンド系は移動平均線などを筆頭に相場の「トレンド(方向)の指針」となるインジケーター。
対するオシレーター系は「売買の指針」として、その時点の売買の偏り(売りが過剰、買いが過剰など)を判断するインジケーターと言われています。
有名どころで言えば「MACD」や「RSI」と言ったものになりますが、この「オシレーター系のインジケーター」には『ダイバージェンス』と呼ばれるシグナル(サイン)があり、
「レートの変動とオシレーター系のインジケーターが逆行する状況」
が、この『ダイバージェンス』に該当します。
この『ダイバージェンス』をアテにしてトレードを行っているトレーダーも多いようで、これを売買のサインとしているツールや情報商材系のノウハウなども少なくありません。
ただ、この『ダイバージェンス』に該当する情報が、
「そもそもどういう状況なのか」
などをよく分からないまま、漠然と「有効なサイン(らしい)」という判断で利用しているトレーダーも多いのが実情のようです。
よって、ここでは、オシレーター系インジケーターの『ダイバージェンス』について、その判断方法や注意点などを解説していきたいと思います。
オシレーター系インジケーター「ダイバージェンス」について。
オシレーター系のインジケーターの有名どころは「MACD」や「RSI」などになりますが、ダイバージェンスの判断が分かり易いのは「RSI」の方だと思います。この「RSI」もそうですが、オシレーター系の指標は基本的に以下のような形でチャートとは別のスペースに表示されます。
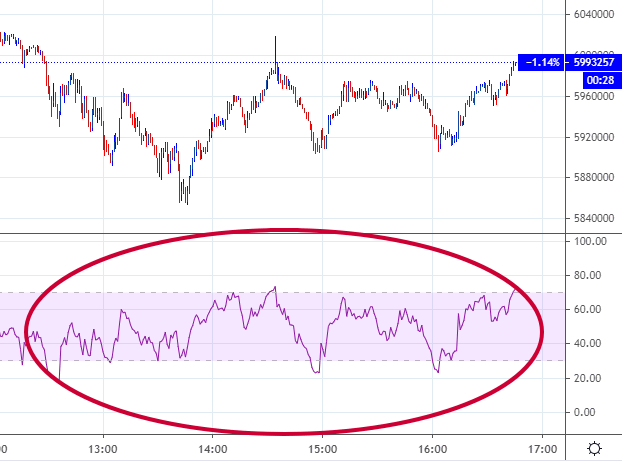
この「RSI」の一般的な見方としてはRSIの数値が70(70%)を超えると「買い注文に過剰な偏りが生まれている」とした上で、RSIを捉える視点では、
「買い注文が納まり、売り注文が強くなる可能性が高い → レートが下がる」
という判断になります。
対して、RSIの数値が30(30%)を下回ると「売り注文に過剰な偏りが生まれている」という見方になり、
「売り注文が納まり、買い注文が強くなる可能性が高い → レートが上がる」
という判断になります。
このようなRSIの見方、判断基準を前提とする上では、RSIの数値が高い時は、
「買い注文が過剰になっている」
という事ですから、必然的にレートは上昇している状況にある場合がほとんどです。
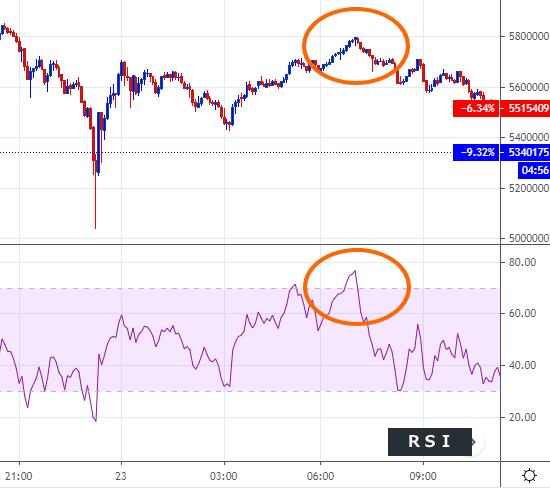
また、同様にRSIの数値が「低い時」は、同じように
「売り注文が過剰になっている」
という事ですから、レートは下降している状況にあるはずです。
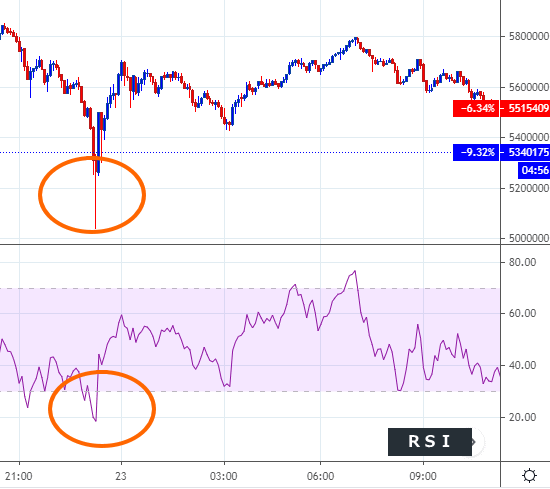
この傾向を前提に捉える上では、
・相場が高値を更新していく時は、RSIも高い数字を維持、または上昇していく
・相場が安値を更新していく時は、RSIも低い数値を維持、または下降していく
という傾向が、レートとRSIの基本的な相関関係という事になります。
ですが、レートの動きとRSIの数値が以下のような形で、逆方向に動くケース。
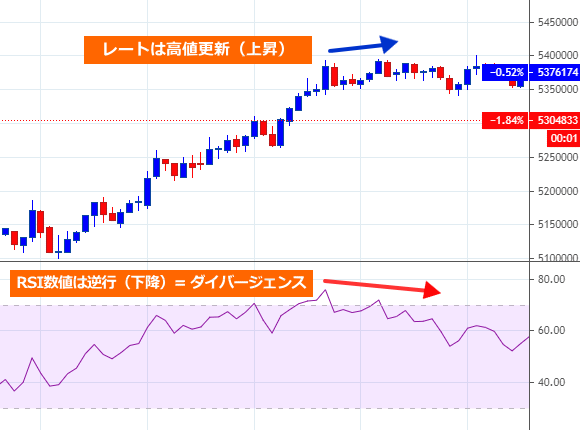
これが「ダイバージェンス」と呼ばれるサイン(ジグナル)で、
・トレンドが「弱まり」や「反転」の可能性
・売り注文と買い注文の傾向が切り替わる可能性
これらを表すサイン(ジグナル)と言われているわけです。
オシレーター系指標で「ダイバージェンス」が生じる理由と要因。
この「ダイバージェンス」が生じる要因は、理論的には何ら難しい話でも何でもありません。各オシレーター系指標の計算式に基づくものとして、そのような状況になるケースが普通に「ありえる」というだけなのが実情です。
ただ、そのオシレーター系指標の計算式に基づく結果が「ダイバージェンス」の現象を生んでいる事自体に「意味がある」という考え方もあり、まずはそこを先ほどの「RSI」の計算式を例に挙げて言及してみます。
そもそも大抵のテクニカル指標(インジケーター)には、それをチャートに表示する上での定められた計算式が存在し、RSIに関しては、以下のような計算式に基づく結果がチャート上に表示されています。
値上がり幅の平均/(値上がり幅の平均+値下がり幅の平均)×100
この「値上がり幅の平均」や「値下がり幅の平均」は一定の同じ期間で算出しますが、一般的には「14日間」または「ローソク足14本分」が基本となっているようです。
(この14日間、ローソク足14本というところが、ある意味では「かなり重要なポイント」になってくるのですが、そこは追って言及します)
この「RSI」の計算式に基づくと「分子」に対して「分母」の数値が大きくなれば、必然的にRSIの数値は小さくなり、その「分母」となる数値が小さくなれば、RSIの数値は大きくなります。
ただ、分子にも分母にも「値上がり幅の平均」が入っているわけですから、この数値の変動は結局のところ「値下がり幅の平均」の大きさで決まってきます。
つまり、計算の対象となる期間(ローソク足14本分)において「値下がり」が無ければ「値下がり幅の平均」も『0』となるため、RSIは必然的に「1×100」の『100%』となるわけです。
よって、相場が常に上昇トレンドを継続しているような時であれば、常に上記の計算式の「分子」と「分母」に「値上がり幅の平均」が加算されていく形となるため、RSIの数値は「上昇」か「維持される」かのどちらかになります。
ですが、この計算式の前提の上で、レートが高値更新をしたにも拘わらず『ダイバージェンスが生じた』という状況は、14日間、または14本のローソク足の平均幅を計算の対象としている関係上、
「大きな上昇幅を加算していた15本前のローソク足による数値が計算対象から外れた」
とう事を意味しています。
要するに、大きな上昇幅を加算していたローソク足が15日前、または15本前のローソク足となった時点で、必然的にそのローソク足によって加算されていた分の数値は「上昇幅の平均計算の対象から外れる」という事です。
厳密に言えば新たに計算の対象となったローソク足の上昇幅よりも、15日前、または15本前のローソク足の上昇幅の方が大きかった場合、必然的に下げ幅の平均値を加算している「分子の数値」の方が大きくなります。
その結果、レートが高値を更新していたとしても、その更新幅がそれほど大きくなければRSIの数値は下がる事になり、その結果として「ダイバーシェンス」のサインが生じるわけです。
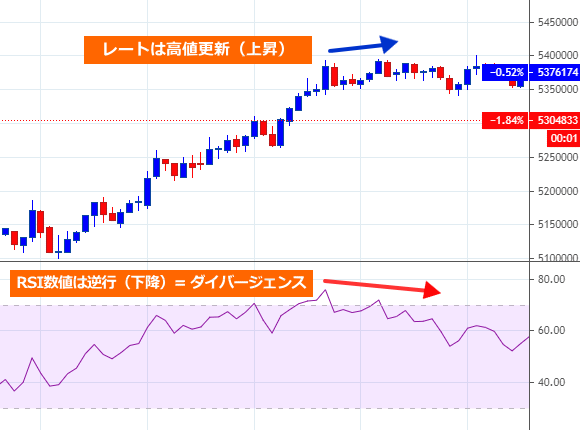
端的に言えば「ダイバーシェンス」という現象は「平均」という計算式を前提としているインジケーターにおいては、計算式の理論上、上記のような状況で必ず生じる現象という事になります。
このような計算上(理論上)の前提において生じる「ダイバージェンス」という現象が、その後の相場の値動きやトレンド動向、トレーダー達の実際の売買を予測する有効な判断材料になるものなのか。
これがそもそもの「根本的な課題」となるわけです。
オシレーター系指標における「ダイバージェンス」の注意点。
ここで言及したようにオシレーター系のインジケーターにおける「ダイバージェンス」は、あくまでも計算上の結果として必然的に表れる現象に他なりません。少なくとも、このような「インジケーター」や「ダイバージェンス」などの現象は全般的に、実際の相場の中で生じているリアルタイムな売買の傾向がそこに表示されているわけではないという事です。
ここで言及した「RSIのダイバージェンス」で言えば、
・平均計算の対象となる15日前、15本前のローソク足の計算対象から外れた事
・新たなに確定したローソク足が新たな平均計算の対象となった事
実質的には、このような「数学的な要因」によって、その現象が現れているに過ぎません。
その点において、新たに確定した「最も近い値動きの範囲を表すローソク足」を計算の対象に入れていく事には、少なからず『意味がある』と考えられます。
ですが、それに伴い「RSI」に関して言えば、
「15日前、または15本前のローソク足の数値を計算の対象から外す」
という事に「値動きの動向」を予測する上での優位性や、それを裏付ける何かがあるのかどうか。
また、そもそも「14日間」または「14本のローソク足」のみを計算対象とする事に、何か「意味」や「優位性の裏付け」があるのかどうか。
こういったところを追及していくと、大抵、この手のオシレーター指標は、
『確固たる理由や優位性の裏付けなどはとくに無い』
というところに行き着きます。
強いて言えば「多くのトレーダーがそのように利用しているから、それが有効という事になっている」というくらいで、それ以上の「裏付け」のようなものは何も無いわけです。
ですから、この手のオシレーター系のインジケーターや、それらのインジケーターを対象とする「ダイバージェンス」などのサイン(ジグナル)は実質的に、
『それがテクニカル分析というものだ』
といった考え方で、余計な理屈は追及せず、素直に「右へならえ」で同じような使い方をするかどうかに集約されてしまうのが実情です。
その上で、ここで言及してきたRSIのダイバージェンスもそうですが、このサイン(ジグナル)によって、相場がサイン通りに動く事もあれば、全くサイン通りに動かない事もあるのが実情です。
そもそも、相場は「上がるか下がるか」ですから、どんな適応なサインを「サイン」と捉えても『相場がサイン通りに動いた(ように見える)ケース』はいくらでもありえるわけです。
ただ「相場の現実」を言えば、相場において一度始まったトレンドが長期間、継続し、上昇を続けていくこと、下降を続けていくことはザラにあります。
要するにRSIの「数値」や「ダイバージェンス」のみをアテにして、その数値やサインに沿った売買を行ってしまうと、
「上昇トレンドの継続、真っ最中に売りポジションを建ててしまう」
「下降トレンドの継続、真っ最中に買いポジションを建ててしまう」
という事にもなりかねません。
結局のところ、RSIの数値やダイバージェンスの現象は、RSIで一般的とされる「14日間」または「14本のローソク足」のみを対象に、その平均値を算出しているが故の数値や現象に過ぎないものです。
その「14日間」「14本のローソク足」という周期に確固たる「意味」や「優位性の裏付け」があるなら別ですが、現実的に考えて「そこには何の意味も優位性も無い」と言うのが実情だと思います。
少なくとも、私はそこには何の優位性も無いと考えていますので「RSI」のようなオシレーター系の指標はもとより「ダイバージェンス」などのサインも、全くトレードの判断には取り入れていません。
もちろん、そこに何らかの優位性を見出し、それなりの確証を持っているなら「RSI」や、それに伴う「ダイバージェンス」のサインをトレードの指針にしていっても良いと思います。
ですが、そのような「裏付け」も「確証」も無い状況で、
・そのインジケーターがどういうものなのか
・それに伴うサインがどのような要因で生じているのか
といった事さえ全く分からないまま、どこかのサイトに書いてあった情報だけを表面的に捉えて、そのような指標やサインに沿ったトレードを行っていくのは「危険」だと思います。
いざ、理論的な部分を追及をしていけば、ここで言及した「ダイバージェンス」のように、相場の動向を予測する上での理論的な優位性は「何も無い」という結論に行き着くかもしれません。
実情として、負けているトレーダーほど、自分が利用しているインジケーターやサインの事を、あまりよく分かっていないケースが多いため、そこは注意するべきだと思います。
もちろん、ここで述べた「RSI」や「ダイバージェンス」への見解は、私の個人的な考えに過ぎないものですが、ここで言及した「理論」などは、事実をそのまま述べていますので、そこも含めて、是非、参考にして頂ければと思います。
あなたにとって「必要な情報」を存分に学んで帰ってください。
以下に、このブログの「目次」にあたるコンテンツ一覧のページをご用意していますので、こちらから「あなたにとって必要な情報(価値がありそうな情報)」を是非、存分に収集して頂ければと思います。>投資家K.U.I(近藤勇一)Official BLOGコンテンツ一覧ページ